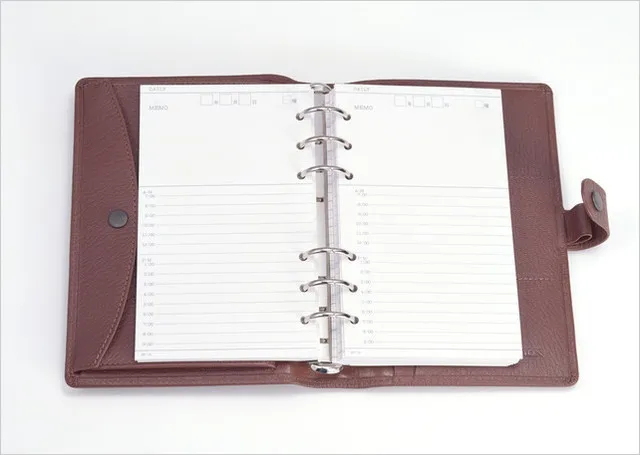借地権・底地の売買、交換 は真の時価評価が重要(土地価格)
2019/02/12
借地権・底地問題はこの分野の専門家である不動産鑑定士が解決 します。
- 下記のような状況になった時どうされますか 誰に相談していいかお悩みではないですか。
- 借地の賃貸借契約の期限満了の時期がきた。 地主さんから借地の返還を求められたが戻すべきなのか。
- 底地を整理したいがどうしたらいいのかわからない。 その底地価格は幾らなのか。
- 借地権を売却したい。地主に買い戻してもらう場合と第三者に売却する場合とどう違うのか。
- 底地と借地権を交換して更地としての所有権にしたいがどうしたらいいのか。
- 借地人が現存の木造建物から鉄骨建物に建て替えるに当たっての地主へ支払う条件変更承諾料はどの程度の金額か。
- 立退料の考え方、その金額はどの程度か。

幣事務所の強み
地主の悲劇(不動産を持っている為の悩み)
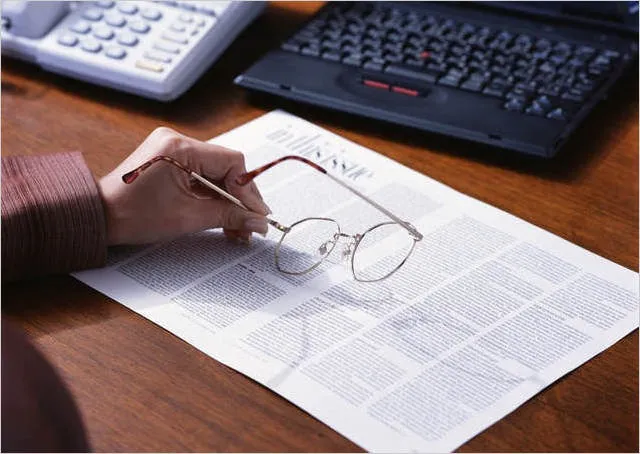
対応策
- 底地の借地人への売却
- 地主の借地権の購入
- 底地・借地権の同時の売却
(1) 借地権とはどんな権利ですか
1. 借地権の成立要件
- 賃貸借契約を締結していること
- 固定資産税・都市計画税以上の地代を支払っていること。
2. 借地権の種類
- 旧借地法の適用のある契約の更新のある借地権(旧借地権)
- 新法の借地借家法の適用のある契約更新のあ普通借地権
- 期間の到来時に消滅する定期借地権

- 普通借地権と定期借地権との差異
- 契約形式
- 普通借地権・・・事由
- 定期借地権・・・公正証書等の書面での契約
- 更新の有無
- 普通借地権・・・有(地主が更新拒否するには正当事由が必要)
- 定期借地権・・・無
- 建物買取請求権
- 普通借地権・・・有(地主の正当事由が認められ借地契約が終了した場合、借地人は地 主に対しこの請求権がある。
- 定期借地権・・・無とすることができる。
3. 新借地借家の改正点
4. 新旧法の相違点
- 平成4年8月1日以前の契約は旧借地借家法が適用される。
- 平成4年8月1日以降の契約は新法の借地借家法が適用される。
- 存続期間の定めがある場合 堅固建物は30年以上 非堅固建物は20年以上
- 存続期間の定めのない場合 堅固建物は60年 非堅固建物は30年
- 更新後の存続期間 堅固建物は30年 非堅固建物は20年と
5. 借地権の対抗要件
6. 借地権は相続できる
2. なぜ、借地権に価格が生じるのか
借地人に帰属する経済的利益とは

- 借地権の基礎となる土地価格借地権価格の価格の基礎となる価格は更地価格と下記のような契約減価された基礎となる価格がありますので注意して下さい。 土地価格(更地価格)はその土地が存する地域は幹線道路沿いで中高層の店舗・住宅地域であるとするとその土地の価格はその土地の最有効使用に基づく価格になるのでその土地が標準的画地並であれば中高層店舗・住宅地としての土地価格になります。それがその土地の賃貸借契約の目的が非堅固建物所有(木造建物)での契約であれば鑑定評価では契約減価と言って上記の更地価格(中高層店舗・住宅地の価格)並には利用ができず、その土地の価値に相応しる土地価格は上記の中高層店舗・住宅としての土地価格に対して非堅固建物(木造)利用の土地価格に修正、すなわち契約減価した土地価格になります。
- 契約減価の修正額非堅固建物から堅固建物(SRC RC)に建て替えるに当たって借地人が地主に支払う借地条件変更承諾料相当額(更地価格の10%)に該当します。
- 借地権割合借地に対して借地人が持っている権利の大きさです。別に法律で定められているわけではありません。借地権の取引慣行がある地域において、借地権の設定時に権利金として借地権割合に応じた金銭が授受されという考え方に基づいているからです。 この借地権割合も非堅固建物所有の場合と堅固建物所有の場合とでは異なります。
父親が亡くなってから10年、この度、母親が亡くなりました。・・・
お母さん名義の借地権付き建物は相続の対象になりますから相続人に継承されますので遺産分割する必要があります。この場合、まずはその借地権付き建物の時価評価をしますがここで問題があります。
借地権は実際に借地契約してしている土地に発生していますが、その範囲(借地面積)が確定してない場合がありますので実測するなりして確定しなければなりません。

借地権Q&A
借地借家法の50年ぶりの大改正が行われた。具体的、主な特徴点は何か
旧借地借家関係を冷静に見れば、明らかに公平性を欠いていた、どちらかと言えば、借地人保護が強く借地人に有利な運用がなされていると言える。
地主からすれば「一度貸したら戻ってこないと思え」と言う考え方が強く、これらの矛盾を改善すべく 以前から借地借家方の改正が検討されていた。それで平成4年に旧借地法が廃止され、新借地法が制定された。改正事項は下記のとおりである。
- 定期借地権制度の創設
- 期限付き借家制度の創設
- 借地権の存続期間の見直し
- 正当事由の明確化
- 地代家賃増減額請求手続きの改善
但し、平成4年に新借地法制定前に契約された旧借地法下での賃貸借契約は旧借地法の契約内容のまま存続することになるので、問題点は多く残っている。ぜひ借地・底地専門の不動産鑑定士 田邉勝也に相談下さい。
借地契約期間20年が経過したら土地は地主に返還するのですか
旧借地法での土地賃貸借契約は更新型の土地賃貸借契約で、借地権は建物の構造によって土地賃貸借契約期間を決めており、木造建物であれば当初契約期間は20年、堅固建物(鉄骨、鉄筋)であれば30年と決められています。
そして土地賃貸借契約期間満了した場合、その時点で土地賃貸借契約が終了するのではなく、地主に正当事由(自己使用等)がなく、かつ借地人が存続して使用することに異議申し立てなく、双方の合意が(更新料等)成立すれば土地賃貸借契約は同一内容で合意更新されます。(合意更新契約)
この前提は建物が建っていること、建物を利用していること、地代をきちんと支払っていることです。
注意
地主の方から契約期間が満了したから建物を解体して、借地権を戻してほしいとの話があったら、先ずは借地権、底地 更新料等の専門家 不動産鑑定士 田邉勝也に相談下さい。
栄光神奈川鑑定
不動産鑑定士 不動産カウンセラー
田邉勝也
TEL 044-589-5436
k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp
旧借地法の借地権は無くならないのか
賃貸借当事者間で具体的な存続期間を定めなかった場合には、法律で存続期間が決まりますが、期間完了前建物が朽廃により消滅したときは借地権は消滅してしまいます。ただ通常は期間を定めて賃貸借契約をしますので「朽廃」での借地権での消滅はまれです。
よくあることは老朽化したので借地人が建て替えを前提での建物の解体ではなく単に解体し、駐車場と利用している場合がありますが、この場合は本来の借地権を放棄していることになり借地県価格が無くなってしまうので注意して下さい。
事前に相談があれば、建物を解体することを止めることは出来たが、借地人の借地に関する知識が不足していたことから、本来は借地権価格での売買が可能であるのに先ばしって行ったことから大損をしてしまった一例であります。
旧借地法は平成4年に借地法の改正があり、旧借地法と同じような更新型の土地賃貸借は普通借地法があり、契約期間が一定期間になり、その期間が満了した時点で借地契約は終了し、借地権価格は発生しない定期借地権が創設されました。
平成4年以前に契約された旧借地法の契約はなくならず存続しています。
旧借地法では地主と借地人間で種々の問題が発生しトラブルになっています。双方の世代が変わり土地賃貸借に対する認識の程度がことなり難しい状況にあります。そんな時に貸地・借地権を専門とする不動産鑑定士 田邉勝也に相談下さい。
栄光神奈川鑑定
不動産鑑定士 不動産カウンセラー
田邉勝也
TEL 044-589-5436
k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp
借地権を売りたいが地主の承諾は必要ですか。
必ず地主の承諾が必要です。この場合、承諾料を支払うのが一般的です。
地主の承諾が得られなかった場合は裁判所の地主の承諾に代わる許可を得ることで、借地権の譲渡ができます。当事者の合意があれば簡易裁判所でもできます。
栄光神奈川鑑定
不動産鑑定士 不動産カウンセラー
田邉勝也
TEL 044-589-5436
k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp
更新料を支払わないとどうなりますか。
更新料を支払う旨の特例がない場合は借地人には法的な更新料を支払う義務はありません.地主に、正当事由がなければ更新拒絶の意義は出せません。正当事由の要件は厳格で、通常は正当事由は認められません。
地主が、更新に当たっての更新料を請求できるのは、更新料支払いの合意がある場合と、合意がない場合はその地域に更新料支払いの慣習ないしは慣習法がある場合としています。しかし、更新料支払いの慣習ないし慣習法を認めた判決はほとんどありません。
更新料支払いの法律的根拠は在りませんが土地賃貸借契約で合意がある場合は、その請求額が「相当」である限り有効とするのが、多くの判決例であり、多くの学説である。しかし、現実は契約書で明文化されていなくても更新料の授受は行われている。それは諸説あるが適正な更新料請求金額ならば借地人は支払った方が最善である。その地域での更新料の土地価格に対する割合を参考に専門家である不動産鑑定士のアドバイスをお受けして下さい。
更新料を払うことでより更新が確実なものになり、その後の円満な賃貸借関係が維持できるので可能な限り支払った方が良いです。
地主から法外な更新料の請求を受け、借地人は誰に相談していいかわからず悩んでいました。御縁があって幣事務所と関係を持つことができ、幣事務所で適正な更新料相当額を提示し、更新料に強い弁護士にお願いして地主との交渉をして頂きました。その結果、調停にはなりましたが適正な更新料に修正されました。
神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
借地権・底地、
相続土地の時価評価、コンサル
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士
田邉勝也
TEL 044-589-5436
mail k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp
- 地代収入から諸経費を控除した純収益の残存期間に対応する利益の現価
- 将来見込まれる権利金、更新料、増改築承諾料等の一時金の経済的利益
- 将来の期間満了等によって借地権が消滅し、完全所有権に復帰することによる 市場性及び担保価値の回復等による経済的利益
- 土地に対する公租公課の増減、
- 土地価格の上昇及び下落
- 経事情の変動、
- 近傍類似地域の地代に比較して不当になったとき、
底地価格を求める手法
第三者が購入する場合の底地価格求める手法
地主さん、借地人さん現行の土地利用に満足していますか。

- 相続すると高額な相続税が課せられるので今のうちに底地を売却し、現金化しておきたい。
- 親の底地を相続したけれど私は自宅を持っているし借地人との煩わしさ、管理に手間がかかる割には収益が低いので売却したい。
底地の売却
借地人への底地の売却
第三者への売却
底地の借地人への売却
借地権と底地の同時一括売却
借地権の一部と底地の権利を等価交換し,各人が所有権を取得する。
借地権・底地の売買する場合 必ず不動産鑑定士に 相談して下さい
借地権取引・交換での借地権価格

借地権を第三者に売却する場合
借地権のみを第三者に売却する場合
借地権と底地権を地主と借地人が共同で売却
借地権と底知権の権利交換
借地権の取引慣行について
借地権の基礎となる土地価格の契約減価
- 地代収入から諸経費を控除した純収益の残存期間に対応する利益の現価
- 将来見込まれる権利金、更新料、増改築承諾料等の一時金の経済的利益、
- 将来の期間満了によって借地権が消滅し、完全所有権に復帰することによる 市場性及び担保価値の回復等による経済的利益と言います。
底地取引においては

底地とはどんな権利ですか。 底地価格についても教えて下さい
底地とはどんな権利ですか、
借地権の附着している土地という。
土地の使用収益を制約する種々の用益権や建物等が存在しない更地とは異なり、地主が所有する土地上に建物所有を目的とする借地権が付着している土地で、完全所有権に対して制約された所有権である。底地は、土地の使用収益から得られる利潤を土地所有者と借地権者とが配分します。
底地価格については、相続税法では、更地価格から借地権価格を控除した価格を底地価格としています。これは単純に所有権価格を借地権価格と底地価格に配分した割合価格です。
不動産鑑定評価基準では、「底地は賃貸人に帰属する経済的利益を貨幣額で表示したもの」を言うと定義付けれている。
「賃貸人に帰属する経済的利益」とは
・地代収入から諸経費を控除した純収益を残存期間に「対応する利益の現価
・将来見込まれる権利金、更新料、増改築承認料等の一時金の経済的利益
・将来の期間満了等によって、借地権が消滅し、完全所有権に復帰することへによる市場性及び担保価値の回復とうによる経済的利益
実際には、借地権、底地をそれぞれが単独に処分すると各権利の制約によって上記の配分割合に比べ低い価格になってしまい、更地価格=借地権価格+底地価格にならない。
底地の売買では下記の2種類の価格が出てきます。
不動産市場での底地売買は大方は底地を借地人に売却するケースが多いが、例外的に底地を借地人以外の第三者に売却する場合があります。この場合の底地の価格は、現在支払われている地代を基にした地代徴収権価格になり、所有権価格割合から借地権割合を控除した底地割合に比べ相当安くなる。併せて支払い地代や契約更新の時期等により底地価格に差が生じる。具体的には、底地を第三者に売却するとした場合の底地価格は更地価格の10%~20%程度になってしまう。
そこで地主が底地を一番高い価格で売却できるのは、借地人に売却する場合と底地と借地権を同時に売却する場合がある。借地人は、底地を購入すると完全所有権に復帰して当該土地の最有効使用が可能となる為、併合に伴っての増分価値を得ることができます。よって、借地人は、底地を第3者が購入する場合の適正価格+増分価格の一部を上限として、割り増し価格で購入しても採算が取れるのです。
以上のとおり、底地を第三者に売却する場合と底地を借地に売却する場合と底地と借地権を同時に売却する場合の底地価格は異なることを覚えて下さい。
地主としては引き続き土地賃貸借契約を存続するとすれば、常時利益率を高める努力をしておく必要があります。例えば、地代は現状からして経済地代にまでいっきに値上げすることは出来ません。よって、更新料、その他借地人が行うことが予定される借地権転売、建物の建て替え等の時期には地主は良く監視して一時金を徴取することで利益率を高めることが出来ます。
地主としては借地人との交渉は大変でしょうから借地権専門の業者(不動産鑑定、不動産コンサル)に委託し、常時的確な対応することが求められます。
神奈川県川崎市で借地権・底地の売買・交換との時価評価、コンサルを得意としている栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士の田邉 勝也です。 どうぞお悩みがあれば相談して下さい。
神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士
田邉勝也
TEL 044-589-5436
mail k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp
1. 底地の相続が発生しました。相続人は複数です 物納か売却かどちらがいいか悩んでいます。
物納に当たっての下記のような要件が必要で審査条件が厳しくなって中々物納がしずらくなってきました。
(要件)
- 地代は地域の標準並みで滞納及び供託されてないこと
- 借地人との法的な係争がないこと
- 隣接地から建物の越境がなく、境界線が明確であること
- 質権、抵当権その他の担保権が設定されてないこと
物納の評価額以上で底地が売却できる地域の物件はあえて物納するより売却の現金で納めることが可能です。そのうえ差額の現金を手元に留保することも出来ます。
底地は地代収入があり、収益性があると思われがちですが、住宅地での地代は固定資産税の3倍程度が適正とされているので資産運用効率は低いです。
ですから底地を売却してその資金を他に運用した方がより、所得向上を計ることができます。相続人が複数、いる場合は実質的には誰かが管理をし、地代収入を配分するなどの煩わしさから親族間に亀裂が生じてしまうケースがあります。
相続の場合は、底地を売却し、分け易い資産にすることが重要です。
2. 共有地の売却に対して共有者が反対している その対応策はないか
共有地の売却で共有者の1人が売却反対 対応策
自分の持分のみの売却は可能であるが、売却価格が低くなるのであまり芳しくない。
いい方法としては測量を行い、持分に応じた底地を分筆し、個々の所有にした上で売却する「共有物分割」がある
- 借地人への売却 手間は掛かるが上記のとおり第三者に売却するよりか高く売却が可能
- 底地専門買取業者への売却早期の売却が可能で、上記借地人への売却が出来ない場合に有効な手段であるが、 借地人への売却価格より低くなる。更地価格の10%程度が多い。
- 共同売却 借地権と併せて売却する方法で借地人の同意等に時間が掛かるが購入者は結果的には 完全所有権の土地を買うのと同じなので購入者は広がり、比較的高値での売却が可能。
借地権・底地の交換
借地権価格はどうして求めるのか
1. 借地権価格の求め方

(1) 借地権取引が慣行化している地域
(2) 借地権取引慣行が未成熟な地域
借地権価格 底地価格 不動産鑑定士が相談にのります
底地の借地人への買取り要求 どうしたらいいのか
地主からの底地買い取りの話、借地状況でのメリット、デメリットはあるが、このようなことはめったにないので検討に当たります。
その買取についての前提条件として建物所有を目的とする賃貸借契約が締結されていること 地域によって借地権取引慣行の程度が異なるので、一概に借地権割合を相続税路線価での借地権割合をそのまま採用することは実態に合わないこともあるので注意して下さい。
契約の内容をも考慮し、適正な底地価格でなければならない。交渉になるので、基本的なことを不動産鑑定士のアドバイスを受けた方が最善です。
簡便的には、底地価格は所有権価格割合100%から借地権割合を控除した割合が底地割合になる。ただし、これは税法上簡便的な求め方なので、不動産鑑定士は実際の底地取引きの実態を調査して底地価格を評価する。底地価格の妥当性、立証性が認められる価格でなければならないのでぜひ不動産鑑定士に相談して下さい。
幣事務所の不動産鑑定士は借地権・底地を専門としているので安心して相談下さい。
川崎市川崎区渡田向町20-3
栄光神奈川鑑定
不動産鑑定士 田邉勝也
TEL 044-589-5436
k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp
借地権・底地に特化し、問題解決に的確なアドバイスをします

- 無償で土地を貸した場合どうなるのか
- 一時使用の場合の問題点
- ゴルフ練習場に建物が建っている場合
- 非堅固建物所有を目的とした契約なのに堅固建物に建て替えた。
- 契約では建物の構造・用途等を定めなかったところ鉄筋の建物を建てはじめた。 用法違反にならないか
- 地代の滞納と契約解除
- 新地主が地代の値上げをしてきたが応じる必要はあるのか
- 地主が理由なくして大幅値上げを要求してきた
- 増改築禁止の特約があるのに改築した。契約解除になるか
- 借地権を無断で譲渡してしまった。
- 借地権を譲渡するに当たって地主の承諾をえるのに支払う名義書換料の相場はいくらか。
- 地主が死亡したらどうなるのか
- 借地人が死亡するとどうなるのか
- 借地上の建物が老朽化してきている。
借地権・底地問題 不動産鑑定士が解決 神奈川 横浜
地主さんの問題
- 地代を上げたいどうすればいいのか
- 底地を買ってもらいたいが誰に売ったらいいのか
- 借地権を戻したいがいい方法があるか
- 借地人が勝手に増改築してしまっているどうしたらいいか。
- 更新時期にきた。更新手続き、更新料はどの程度か
- 底地と借地権を交換したいがどうすればいいのか
借地人の問題
- 借地権を譲渡したいがどうすればいいか
- 底地を買って所有権にしたいが。
- 借地権を売ろうとしたが建物登記と現況が違っている。
- 更新料は払う必要があるのか
- 借地契約の更新がきれた。地主さんから借地の返還を求められたが
- 借地上の建物を建て替えたいが、借地でもローンを組めるのか
- 借地権を複数人で相続した問題点は
----------------------------------------------------------------------
栄光神奈川鑑定
住所:
神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
電話番号 :
044-589-5436
----------------------------------------------------------------------